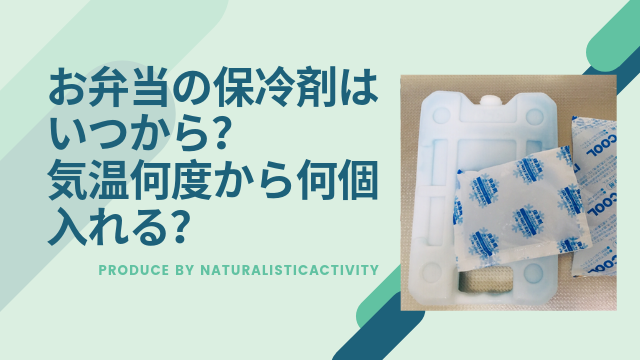お弁当に保冷剤を使うことがありますが、保冷剤はいつから入れ始めるのがいいか知っていますか?
食べ物が腐りやすくなる梅雨の時期から?それとも暑くなってきてから?
気温が何度になれば入れ始めるべきなのか悩むところですが、気温が20℃以上になってきたら、保冷剤を入れていきましょう。
今回はいつからお弁当に保冷剤を使い始めるのがいいかその時期と具体的な気温、保冷剤の大きさ・個数によってどれくらいの保冷効果があるのかをまとめましたので、詳しく解説します!
お弁当の保冷剤は何度から?20℃以上
お弁当に保冷剤を入れ始める時期は、4月でも20℃を超える日が多くなってきたので、気温で判断していきましょう。
さらに、25℃以上のときは、必ず保冷剤を使用すること!
その理由は、食品は10℃を超えると細菌が繁殖しやすくなるため、保冷剤で温度を10℃以下に保つことが重要です。
食中毒が増えるのはいつからかというと、毎年食中毒の被害が多くなるのは6月~8月頃です。
- 保冷剤を入れる気温の目安は最高気温20℃以上
- 湿度が高いと菌が発生するので、雨の日は要注意
- 車の中、体育館の中は外気温が20℃以上

しかし最近は、温暖化の影響で3、4月頃から急に気温が高くなる日があります。食中毒には流行時期がありますが、食中毒自体は1年中発生しています。
5月より前でも、その日の気温や湿度に合わせてお弁当に保冷剤を入れたり入れなかったりする日を作ることが大事です。
食中毒の菌は30℃〜40℃が増殖するのに適した気温になります。
特に気温35℃前後が菌が大好きな環境になります。
夏場はずっと食中毒の菌が発生しやすいのは、、菌にとってとてもいい環境だったからなんですね。
湿度も関係する!
湿度は80%前後から菌が増殖しやすく、湿度が高くなればなるほどたくさんの菌が発生します。
雨の日は特に菌が発生しやすくなるということですね。
天気予報でその日の最高気温が25℃と出ている場合、バッグの中でお弁当を保管をしているとバッグの中は25℃以上の温度になりますので、外気温が25℃以上になるときに保冷剤を使うと覚えておきましょう。
しかし、お弁当を車の中や部活動をしている体育館の中など、外気温よりも室温の方が高くなる可能性のある場所に置きっ放しになってしまう場合は、要注意です。
こういった場所は湿度も高くなりがちですので、その場合は外気温が20℃以上を目安に保冷剤を使うことをオススメします。
何月まで保冷剤を入れるべき?
保冷剤が必要なのは5月から10月頃まで。
特に真夏は必須です。4月や11月でも暖かい日は使用をおすすめします。
一方、12月〜3月の冬場は気温が低いため、保冷剤を入れなくてもいいです。
保冷剤は何時間もつ?
保冷剤のサイズや環境によりますが、小型のものなら2〜3時間程度、中型なら4〜6時間持ちます。
保冷バッグと併用したり、複数個使うことで6〜8時間冷たさを保てることもあります。
お弁当に保冷剤を使うのを5月からにすることで、食中毒が流行する前から対策をとっておき、お弁当を守れるということですね。

クーラーの効いた部屋で過ごすのか、炎天下の室内に放置することになるのかといった環境でも変わりますので、少しでも心配だなと思うときは保冷剤を入れておくと安心ですね。
お弁当の保冷剤を何個入れる目安は?
保冷剤をお弁当に入れるとき、いくつの保冷剤を使えば、お弁当の時間まで保冷効果が保てるのでしょうか。
保冷剤の目安はこちらになります。
- 30g(5cm×12㎝) 約1時間半
- 50g(7.5cm×11cm) 約2時間半
- 100g(9cm×14cm) 約3時間
- 300g(12cm×17cm) 約6時間
上記は気温20℃で、保冷バッグを使用したときの目安です。

保冷剤は大きいものほど保冷効果があり、たくさん入れるとその分保冷効果がアップしますが、お弁当が冷えすぎてしまっても困ります。
お弁当がよく冷えているなというときは、食べる30分~1時間前に保冷剤をお弁当から出しておくといいでしょう。
保冷剤がお弁当の時間にうまく溶けてくれる個数の例をあげます。
- 6時頃に作り、7時に出発、12時にお弁当を食べるとき(お弁当は常温で保管)
→50gと100gの保冷剤を1つずつ使う - クーラーの効いていない車の中に置いたままになる場合
→室温が50℃以上になりますので、同じ時間の保管でも300gの保冷剤を用意しておいた方がいいですね。
50gと100gの保冷剤を入れると約4時間近く保冷効果があると考えられますので、食べるときに冷えすぎていない程度の保冷効果が期待できます。
お弁当の持ち出し時間が長い場合や暑い環境に置いたままになる場合は、保冷効果が長続きするよう、大きい容量の保冷剤を用意しておき、お子さんやご主人に食べる30分~1時間前に取り出すよう伝えておくと安心ですね。
以下に「2. 保冷剤を入れたデメリット」について、より詳しく、現実的な例や原因・対策を交えて解説します。
保冷剤を入れたデメリットを詳しく解説
保冷剤はお弁当を安全に保つために欠かせない存在ですが、使い方によっては「美味しさ」や「食感」が損なわれることも。ここでは、実際に起こりやすい4つのデメリットを深掘りしてご紹介します。
美味しくない
冷えることで味が落ちることがあります。
- 冷めた揚げ物が「ベチャッ」としている
- ハンバーグや炒め物が固く感じる
- 卵焼きの甘みが薄くなったように感じる
これらの原因は、保冷剤でお弁当全体を冷やすと、油分や調味料が固まり、香りや風味が弱まることがあります。
食材が冷たくなることで、舌の温度と合わず、味を感じにくくなるのも一因です。
対策として、
- 味つけはやや濃いめにする(冷えると薄く感じやすいため)
- 揚げ物や炒め物は衣を薄めにする、水分をよく切る
- 食材の中まで冷えすぎないよう、保冷剤の位置や数を調整する
冷えすぎ・冷たすぎる
冷えすぎて食べにくいことも。
- ご飯が冷たくて食べにくい
- サラダや煮物が「冷蔵庫から出した直後のような味」
原因として、保冷剤の過剰使用や、保冷剤を弁当に密着させすぎると、食材が冷えすぎてしまいます。特に、気温がそれほど高くない日でも同じ保冷対策をすると、逆に冷たくなりすぎることがあります。
対策として、
- 保冷剤は弁当箱に直接当てない(紙やタオルを1枚挟む)
- 季節に応じて個数・サイズを調整する(春・秋は1個、小さめでOK)
です。
ご飯が固くなる
でんぷんの劣化により、保冷剤を使うことでご飯が固くなります。
- お弁当の白ごはんがパサパサしている
- おにぎりがボソボソして食べづらい
ご飯は冷えると「老化」と呼ばれる変化が起き、でんぷんが結晶化して硬く・乾燥した状態になります。これは冷蔵庫に入れたご飯がパサつくのと同じ現象です。
対策として、
- ご飯は完全に冷ましてから詰める
- 保冷剤とご飯の間に緩衝材(紙・布)を挟む
- おにぎりには梅干しや昆布など水分を補う具材を使うと◎
水滴(結露)が出る
保冷剤を入れることで、弁当袋や中身が濡れるがあります。
- お弁当の外のタオルが湿っている
- 弁当箱の中に水がたまっている
- ラップや仕切りがべちょべちょになる
原因は、冷えたお弁当と外気の温度差で「結露」が発生します。
湿気がこもると、食材の食感が落ちるだけでなく、カビや雑菌の原因にもなりかねません。
対策として、
- 保冷剤をタオルや不織布で包む(吸湿効果あり)
- 弁当箱と保冷剤の間に吸水シートを入れる
- 弁当の中身に水分の多い食材(果物・サラダなど)を直接入れない
です。
保冷剤の入れ方も詳しく解説
保冷剤は「どこに・どのように・何個」使うかで、保冷効果が大きく変わります。
お弁当を美味しく・安全に保つために、正しい入れ方をマスターしましょう。
どこに入れる? 上か下か?
基本は上に置くのが効果的です。
冷気は重いため上から下に流れる性質があります。
そのため、保冷剤は弁当箱の上に乗せるのが基本です。
より効果的な方法
- 上下でサンドする:弁当の上下に保冷剤を挟むと全体が均等に冷える
- 側面もカバー:大きめの保冷剤なら、側面を覆うようにするとより安心
- 直接触れさせない:保冷剤が食材に当たると冷えすぎるので、紙ナプキンやタオルを1枚挟むと◎
保冷バッグなしの場合
保冷バッグがない場合でも、工夫次第で保冷効果を高められます。
方法
- 弁当箱と保冷剤をアルミホイルやタオルで包む
- **発泡スチロール箱やクーラーバッグ代わりの紙袋(二重)**に入れる
- 厚手の布製トートバッグ+内側にアルミシートを敷くと簡易保冷効果あり
ワンポイント
- 直射日光を避け、日陰に置く or 保冷袋ごと冷やした状態で持ち運ぶとさらに効果UP
何個入れる?
気温や使用時間によって、必要な保冷剤の個数は変わります。
| 状況 | 推奨個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 春・秋(20℃前後) | 1個(中サイズ) | 通常の昼食ならOK |
| 夏(30℃以上) | 2〜3個(中〜大サイズ) | 上下+側面に配置 |
| 保冷バッグあり | 1〜2個で十分 | バッグの断熱性により減らせる |
| 冷房の効いた室内保管 | 1個でも可 | 外よりリスクは低い |
※ 100gの保冷剤=約2〜3時間が目安
タオルの使い方
タオルは断熱・吸水・滑り止めと、一石三鳥のアイテム!
使い方アイデア
- 保冷剤と弁当を一緒にタオルで包む
- 保冷剤の下に敷いて結露を吸収
- 弁当箱をタオルで「すき間埋め」することで保冷空間を密閉
おすすめは
- フェイスタオルやハンカチでしっかり包む
- 速乾・吸湿タイプのタオルや手ぬぐいも◎
入れ方のOK例・NG例
OKな例
- 弁当箱の上下に保冷剤+タオル包み
- 保冷バッグ+タオルで断熱+日陰に保管
- 凍らせたゼリーや飲み物と一緒に入れる
NGな例
- 保冷剤が直接おかずに触れている(冷えすぎる)
- 保冷剤1個だけを真横に置いている(片側しか冷えない)
- 保冷剤がないまま直射日光に放置
保冷剤は「ただ入れる」だけでなく、「どこにどう配置するか」がポイントです。
季節や状況に合わせて、適切な個数と位置、断熱素材との組み合わせを工夫することで、お弁当をより安全に・美味しく保てます。
保冷剤の代用品は?
保冷剤が手元にないときは、凍らせたペットボトルやゼリーがおすすめです。
飲み物も冷たくなるので一石二鳥。
凍らせたこんにゃくゼリーなど、食べられる保冷剤も便利です。
保冷剤を忘れたらどうなる?
夏場に保冷剤なしで長時間放置すると、食中毒のリスクが高まります。
特に4時間以上の常温保存は要注意。酸っぱい匂い・変色・異臭などがある場合は、絶対に食べないようにしましょう。
念のため、梅干しや酢飯など、傷みにくい食材を取り入れておくと安心です。
冬でも保冷剤は必要?
外気温が10℃以下なら、基本的に不要です。ただし、暖房の効いた室内に長時間置いておく場合や、詰めたおかずが熱いままの場合は注意。お弁当はしっかり冷ましてからフタをしましょう。
最強の保冷対策はこれ!
お弁当の保冷力を最強に高めるためには、以下のアイテムを組み合わせましょう
- 保冷バッグ(断熱タイプ)
- 大型保冷剤を上下に配置
- 凍らせたペットボトルやゼリーを同梱
- 食材はしっかり冷ましてから詰める
- 全体をタオルで包む
これで、真夏でも安心してお弁当を持ち運べます。
保冷剤は適度に賢く使うのがポイント
保冷剤は確かに便利ですが、入れすぎたり、置き方を間違えると、せっかくのお弁当が「冷たくて美味しくない」ものになってしまいます。
「季節・天候・食材」に合わせて調整しながら使うことで、安全性と美味しさのバランスを保てます。
ご希望があれば、各項目を図や写真付きにしたり、Q&A形式にもできます!どう使いたいか教えてください。
100均でお弁当用の抗菌シートも販売されていますので、抗菌シートで菌を出にくくしながら保冷剤を使い、お子さんや旦那さんに安心して食べさせてあげられるようにしたいですね。